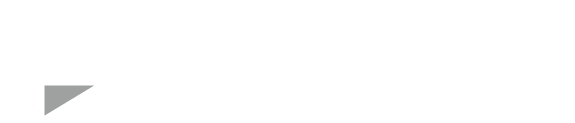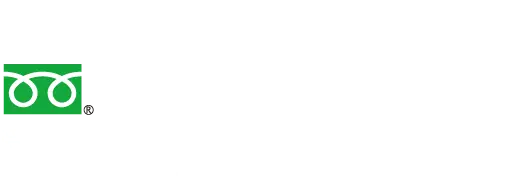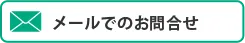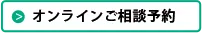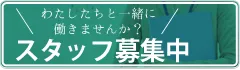2025年問題と生前対策のすすめ
2025/07/29
2025年問題とは?
皆さんは2025年問題と言葉を耳にしたことはありますか?
2025年問題とは、国民の約3人に1人が65歳以上、
5人に1人が75歳以上の後期高齢者となることで
日本社会が直面する高齢化の課題のことを指します。
例えば、医療・介護の需要増大、社会保障費の膨張、労働力不足が大きな懸念材料です。
また、地域社会やインフラの老朽化など、多方面での対応が急務となっています。
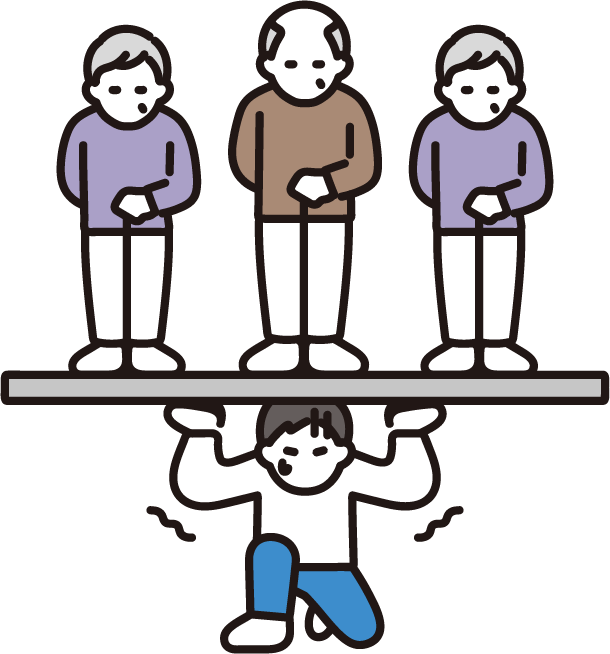
また、超高齢化社会を迎えた日本では、
認知症を発症する人の数も年々増えており、
預金が引き出せない、不動産を処分できない
といったリスクも高まっています。
認知症は身近な病気となりつつあります
厚生労働省の統計によれば、
2025年には認知症高齢者が約700万人に達すると見込まれています。
これは65歳以上の高齢者のおよそ5人に1人にあたります。
認知症は、本人のみならず家族や周囲の人々にとっても大きな課題となる可能性がある、
非常に身近な病気になっています。
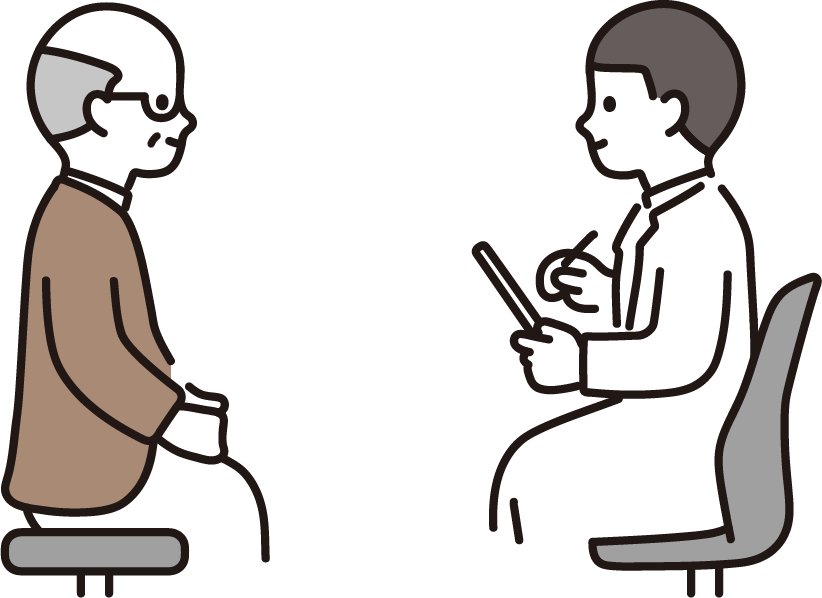
認知症の進行により、判断能力が低下すると、財産管理や日常的な契約行為が困難になります。
契約ごとを行うためには、本人の財産を保護する目的で
「成年後見人」の選任が必要となる場合があります。
もっとも、成年後見人は家族であれば務められるわけではありません。
家庭裁判所が本人のために必要な保護や支援などの事情に応じて選任されます。
そのため、弁護士など第三者が財産管理を務めることとなるケースも少なくありません。
また、後見事務を行った場合の報酬も発生します。
では、信頼できる家族に財産管理を行ってもらうための手段にはどのようなものがあるのでしょうか。
信頼できる家族に財産を管理してもらうには?
認知能力が低下したあと、確実に信頼できる家族に財産を管理してもらうためには、
①事前に任意後見人を定めておくこと
②信託契約を結んでおくこと
が有効です。
任意後見契約は、本人が判断能力を有している間に後見人を選び、財産管理や生活支援の内容を取り決める制度です。
判断能力が低下した場合には、選任された任意後見人が本人の意思を尊重しながら支援を行います。
なお、任意後見契約の内容どおりに業務を行っているかを監督する任意後見監督人の選任により任意後見契約の効力が生じます。
信託契約を結ぶことで家族だけで財産管理を完結することが可能です。
認知症発症後も、信託契約に基づき受託者が財産管理を行うため、口座凍結の心配がなくなります。
また、不動産の管理を信託契約に組み込むことで、受託者が不動産を管理できるようになります。
なお、どちらも、認知能力が十分に認められる間に契約を結んでおく必要があります。
相続後の手続き軽減も生前対策です!
相続に向けた準備も、将来のご家族や相続人の負担を軽減するための重要な生前対策です。
相続が発生すると、相続人は遺産分割の話し合いや手続きなど、
多くの時間と労力を費やすことになります。
こうした負担を減らすためには、事前に準備を進めておくことが効果的です。
一例として、遺言と生命保険の活用をご紹介いたします。
遺言書は、財産の分配方法や相続人への想いを明確に伝えるための重要な手段です。
遺言書で財産の分配を事前に指定し、家族間のトラブルを防ぐことが可能です。また、事前に遺言で執行者を指定しておくことで、相続人の方がスムーズにお手続きをすすめることが可能です。生命保険に加入しておくのも有効な手段の1つです。
生命保険金は、受取人固有の財産とみなされるため、遺産分割協議の対象外となり、受取人が速やかに資金を受け取ることが可能です。そのため、相続発生時に必要な納税資金や葬儀費用の確保にも役立ちます。 また、生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、相続税対策としても有効です。計画的な生命保険の活用で、安心できる相続準備を進めましょう。まとめ
2025年問題は、社会全体が取り組むべき重要な課題であると同時に、
個人や家族が直面する現実的な問題でもあります。
「まだ先の話」と考えず、今できることに目を向けてみませんか?
安心して老後を迎えるために、ぜひお気軽にお問い合わせください。
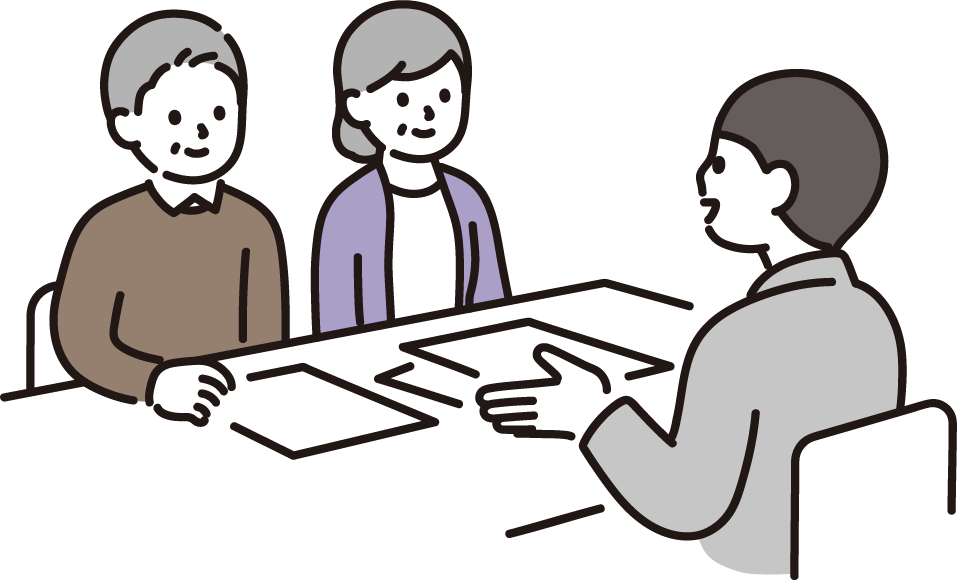
相続のお悩み、無料相談で解消しませんか?
広島の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門家集団、行政書士法人ライフは、無料相談実施中